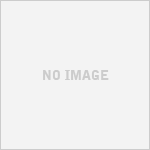梅干しの漬け方には簡単な方法もある?! 自家製の梅干しを楽しもう!
公開日:
:
便利技
日本の食卓には欠かせない梅干し・・・
ご飯をいっそうおいしくしてくれるので
いつも家に常備している!という人も多いはず。
その梅干し、自分で漬けて食べたくないですか?
自分で漬けたものならよりおいしく感じるはず。
今回は梅干しを自分で漬けてみたいけど、
簡単な方法がいい!という方に、
抑えておくポイント、
簡単な漬け方をご紹介。
ぜひ参考にしてくださいね!
梅干しの漬け方には簡単な方法がある?
塩分や容器は?
梅干しを付ける際、
気を付けておきたいポイントがあります
まず「減塩をしないでちゃんとした量の塩を使う」こと。
梅の20%の量がちょうどいいですね。
塩分はもちろん気になるところですが、
減塩してしまうと、
梅から水分がなかなか出てこなかったり、
早く傷んでしまったりします。
20%の量の塩で漬けることによって、
常温で何年も保存できます。
2つ目は「容器を使って漬ける」こと。
レシピによってはシップロックを使って
自家製の梅干しを漬けるものもあります。
梅が袋のなかで密閉されますが、
梅から水分が出てくるときに傷みやすくなります。
気温の変化にも気を付けなければいけません。
しっかりした専用の容器がない場合は、
ボールや鍋で漬けることもできますよ!
梅干しを自家製で楽しむ簡単なレシピ
ではさっそく漬け方をご紹介していきましょう!
用意しやすい分量で記載しますが、
容器の大小もあるので、各材料を調整してくださいね!
【材料】
梅・・・1kg
塩・・・200g
赤しそ・・・200g
塩・・・40g
【下準備】
梅が青い場合は、
皿に並べて常温でしばらく置いておきます。
黄色くなるまで熟させます。
【作り方】
①梅に傷をつけないように丁寧に洗い、
ペーパーで水気をしっかり拭き取ります。
その後竹串などでヘタを取ります。
②清潔な容器に塩と梅を交互に入れていきます。
最後、一番上には塩がくるように重ねていきます。
上から重しをして蓋をし、
梅から水分が出てくるまで2~3日ほど置きます。
③赤しそは枝を取って洗います。
こちらも水気をしっかり拭き取ります。
分量(40g)の半分量の塩と赤しそをよく揉み、
水分をしっかり絞ります。
残りの塩を加え再度手でよく揉み、
水分をしっかり絞ります。
④③の赤しそを漬けていた梅の上にかぶせます。
再び重しをして、梅雨明けを待ちます。
⑤晴れの日に梅と赤しその両方をざるに広げ、
数時間~3日ほど天日干しします。
天日干しをするときは、天気予報を確認して、
晴れの日が続く日を選んでくださいね!
途中で雨になると干せなくなってしまうので・・・
まとめ
いかがでしたか?
今回はご自宅で梅干しを簡単につける方法を
ご紹介しました!
梅干しって一見難しそうですが、
材料さえ揃えてしまえば
意外と簡単に漬けられるんです。
ただし、ポイントを押さえて、
できるだけ長持ちする方法で作りたいですよね。
ぜひ今回ご紹介した方法で、
味の変化を楽しみながら味わってくださいね。
関連記事
-

-
雛人形の折り紙の折り方☆ 誰でも簡単にできる折り方とは?
雛祭りに欠かせない雛人形や雛飾りを折り紙で簡単に作れたら・・・。なんて思いますよね!でも難しそうだし
-

-
免許証住所変更の代理は委任状でいいの?委任状の書き方と持ち物をお伝えします
年度替り、皆さん新生活を始められた方も多いと思います。 新生活で、大変なのが引越しですよね。
-

-
三井アウトレットパーク木更津に行こう! 営業時間やアクセスをチェック
異常なくらいあつーーーい今年の夏は、 外に出たいけど出れない・・・ 葛藤に悩まされますよね。
-

-
失敗なし!お歳暮に喜ばれる缶詰・瓶詰めギフト
寒い冬が近づくと、お歳暮に贈る品を決めなくてはいけませんね。 毎年のことですから、頭を悩ませる
-

-
壁に収納スペースを簡単手作り! DIY初心者さんにもおすすめの方法!
アパートなどで部屋の収納スペースが十分にない場合、 あなたはどうやって整理整頓をしますか?
-

-
クリスマスに失敗なし!炊飯器で作るローストビーフ
クリスマスが近づくと、当日はどんな料理を作ろうかと悩みますね。 クリスマスの定番料理といえるの
-
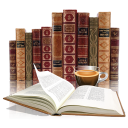
-
ワンルームで家具配置のコツは?
今年も春の卒業・新入学・就職のシーズンがもうすぐそこまで来てますよね。 皆さん、新たな生活への期待
-
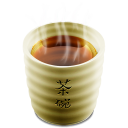
-
煎茶と玉露の入れ方、ついでにほうじ茶も。
お茶は誰が入れても同じではありません。 茶葉のうまみを引き出すポイントを知っておくと素敵なおもて
-

-
主な桜の種類を一覧でチェック!早咲きはいつ頃から楽しめる?
もうすぐお花見の季節ですね!ですが「シーズン真っただ中は忙しくて、とてもじゃないけどお花見には行って
-

-
大掃除は年末だけじゃない!オススメ夏の大掃除
一年の汚れを落として新しい年を気持ちよく迎えようと行う大掃除。 毎年重い腰が上がらないという方