七夕の笹を青々と長持ちさせるには? ポイントは水分?!
公開日:
:
イベント
そろそろ七夕の季節・・・
ご家庭では笹の葉を準備される方も多いはず。
せっかく七夕に笹の葉を飾るのですから、
少しでも長くきれいに保ちたいですよね!
今回は七夕に使う笹を
長持ちさせる方法をご紹介します!
今まで本物の笹を飾るのはちょっと・・・
と思っていた人も必見ですよ!
目次
七夕の笹を長持ちさせるには
水揚げをする?
そもそも笹は普通に飾っておくとどうなるのか?
笹はとても水揚げが悪い植物なので
切るとあっという間に葉が枯れてしまうのです。
少しでも長持ちさせるために、
ここでは3つの方法をご紹介します!
1.酢水に浸けて生けておく
一番簡単な方法ですね。
今までお水だけだったところに
お酢を加えるだけでできる方法です!
この時注意したいのが、濃さ。
お水に少し垂らすだけではなく
水:酢=3:2くらいの濃さでお酢を入れましょう。
かなり濃いですが、
笹の場合濃い酢水に浸ける方が長持ちします。
2.笹全体を水に浸け、新聞紙で包む
七夕の飾り付けをする直前まで
笹全体を水に浸けておきます。
大きなタライがあればいいですが、
なければお風呂場を使ってもいいですね。
水につからない部分は濡らした新聞紙で包んで、
全体が水に触れているようにすることがポイントです。
この方法で劇的に日持ちする、というわけではありませんが、
普通に水に差しておくだけより、
葉をきれいな状態で保存することができます。
3.節に穴を開けて熱湯を通し、水を入れる
こちらの方法は笹よりも
ある程度太さのある竹を使う時に有効ですね。
キリなどで竹の内側の節に穴を開けます。
竹の中をひとつながりの空洞にするイメージですが、
すべての節に穴を開けるのはなかなか難しいので、
開けられる範囲で!
穴を開けたらその中に熱湯を通します。
これで中の薄皮がはがれて、
内側から水分を吸収しやすくなります。
ただし、熱湯を流すのは2~3分にとどめてくださいね。
あまり長時間だと竹の色が悪くなってしまいます。
そして竹の下の部分を水に差して、
上からも水をたっぷり注ぎます。
上下両方から水を入れて、
できるだけ中を水で満たすようにしましょう。
七夕の笹を長持ちさせるには水分がポイント?
以上の3つが、
笹を長持ちさせるための方法です。
要するに、
【笹(もしくは竹)にたくさん水分を吸収させる】
という点が共通していますね。
普通の花は茎の部分を水に浸けると水を吸ってくれますが、
笹の場合はなかなか水を吸ってくれません。
なので、いかに水分をよく吸収させるかが
ポイントになってきます。
まとめ
今回は七夕に使う笹をできるだけ長持ちさせる方法を
ご紹介してきました!
簡単に実践できる方法もあったので、
今年からご自宅で笹を飾ってみようと思った方も、
ぜひ試してみてください!
少しでも長く、
七夕ならではの光景を楽しみたいですね!
関連記事
-
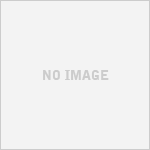
-
沖縄美ら海水族館オキちゃんショーのため地図必須!ベビーカーはおすすめできません!
私は魚が大好きな30代前半の主婦です。 私がおすすめしたいスポットは沖縄美ら海水族館です。
-

-
絶対に見てほしい海水浴場の持ち物はコレ 子供と海を120%楽しむために
夏になると行きたくなるのが海ですよね。子供たちも待ちに待った夏休みで楽しみにしているのではないでしょ
-
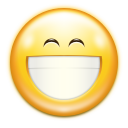
-
送別会で挨拶 送られる側の例文を紹介。マナーとして寸志は払うの?
春先になると、年度替りですね。同時に皆さん新生活がスタートしますね。 退職される方や、人事異動で今
-

-
ゴールデンウィークでも混まない穴場とは!? 関西デートのおすすめスポット
ゴールデンウィークになるとまとまった休みを取れるため 彼女とデートに行くには絶好の日ですよね。
-

-
神戸イルミナージュのチケット購入方法。混雑はするの?
神戸の冬の夜といえば、「神戸イルミナージュ」。 2011年から始まった、神戸フルーツ・フラワーパー
-

-
歓送迎会の司会進行や挨拶などのコツ 流れが大事です。
新年度が始まると歓送迎会をする会社がほとんどです。その際に慣れない司会進行や挨拶をすることになるなん
-

-
ゴールデンウィークにおすすめ! 関西に日帰りでも楽しめるスポット
ゴールデンウィークになると まとまった休みをとれる人が多いと思います。 ですが宿泊をしてのお
-

-
関東の紅葉時期(2014年)
暑ーい夏が終わり、日々だんだんと涼しくなってくると、 どこかに出掛けたくなりますよね! せっ
-

-
結婚式の披露宴に定番の 余興ビデオはiPhoneで簡単! 失敗しない作成方法とは?
友人の結婚式の余興ビデオを頼まれた・・・! 大切な友人に喜んでもらえるようなものに
-

-
伊勢崎花火大会の場所取りすべき穴場を調べた。渋滞は発生する?
群馬県で最も人気の花火大会が「いせさき花火大会」です。 スターマインを中心に約1万発が打ち上げ



